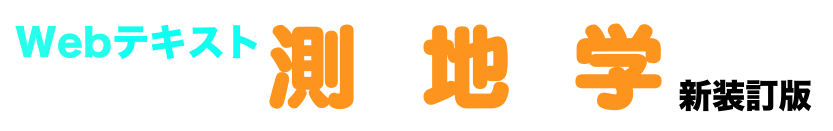PALSARがもたらしたもの —氷河/氷床編—
北海道大学理学研究院 古屋正人
極域の氷河氷床や中緯度の山岳氷河を, 広範囲に定量的かつ継続的にモニターすることの重要性が地球温暖化問題の高まりとともに強調されている. 各種の新しい宇宙測地技術がその目的に貢献しており, GNSSを用いた地上測量, 衛星高度計を用いた氷厚や氷の体積変化の高精度測定, GRACEを用いた氷質量そのものの増減の測定もその一例である. 本稿ではSARがもたらした氷河氷床モニターや氷河学への貢献について, 背景や経緯とともに振り返る. 1990-2000年代は欧州のERS1/2やカナダのRadarsatといった海外のSAR衛星データによる貢献が大きかったが(Joughin et al., 2010), 日本が打ち上げたPALSARもLバンドの特長を生かして多くの成果をもたらした.
InSARを用いた雪氷圏の観測は, Massonnet et al がLanders地震による地震時地殻変動を発表したのと同じ1993年に米国ジェット推進研究所のGoldstein et al (1993) によってSCIENCE誌に報告された. Goldstein et al. (1993)は欧州宇宙機構(ESA)のERS1のデータにInSARの手法を適用することで, 西南極のRutford Ice Streamでの流動速度分布と接地線(Grounding line)の位置が得られることを示した. 氷河の流動速度はそのダイナミクスの理解にとって基本的な観測量であるにも拘らず, 従来は氷上に測量機器を設置する必要があったため, 広範囲を高頻度に測定することは困難だった. また, InSARによる接地線の検出は, 海洋潮汐で上下に動く棚氷と上下に動かない陸側の氷の境目が顕著に現れることをその目印とする. 海側の氷(棚氷)と陸側の氷の境界である接地線の位置がどう変化するかは氷河の盛衰を反映する一つの重要な指標であるが, 地表から直接見ることはできない. SAR画像が光学画像に比べて全天候かつ昼夜を問わずに取得できる点は従来から強調されていたが, InSARによって流動速度や接地線といった新たな物理量が観測できることでSARデータに重要な付加価値が生まれた. ただし, Goldstein et al. (1993)でも触れられているように流動速度が年間1kmクラスの速い流れに対しては, 数十日程度の回帰周期の間に干渉縞の空間勾配が大きくなりすぎて, 位相アンラップが困難になり, 変位量が定量化できなくなる. 前述のERS1の運用では氷河流動の検出のために, 3日後に再度データを得るIce mission, 1日後にERS2が同一シーンを撮像するTandem missionが企画され, 回帰周期の短いInSAR画像が取得された. また, 一部の氷河では地形勾配が非常に小さいので地形効果を無視できたのに対して, 標高差を伴う氷河に対しては, 数値地図がないと補正できないために変位量も定量化できない. 現在でこそほぼ全球にわたる数値地図が利用できるようになったが, 2000年代の半ばに漸く北緯南緯60度以内に限られるSRTMによるDEMが利用できるようになった. したがって, 氷河流動速度の空間分布が実際に得られるためには, 幾つかの技術的進展が必要で, 南極氷床の流動速度分布の全容が明らかになったのはごく最近のことである(図1, Rignot et al., 2011).
1. 氷河流動の抽出方法
前述のように数10日程度の回帰周期をもつ衛星SARデータからは, 変位量が大きすぎて位相データに基づくInSARの手法では氷河流動速度を抽出することは困難になる場合がある. それに代わって適用されるのが, 画像マッチング(Matching)に基づく変位抽出で(Michel and Rignot, 1999; Tobita et al., 2001; Strozzi et al., 2002; 小林ほか, 2011), 「ピクセルオフセット法」「スペックルトラッキング法」「オフセットトラッキング法」などとよばれる. ピクセルオフセット法の測定精度は, 位相データを用いるInSARに比べれば劣るとはいえ, 任意性の高い位相アンラップが不要であることや画像同士の相関さえ高ければ変位量の検出限界は10m以上(Tobita et al., 2001)にまで達することから, 流動速度検出にとってはInSARよりも頻繁に使われている.
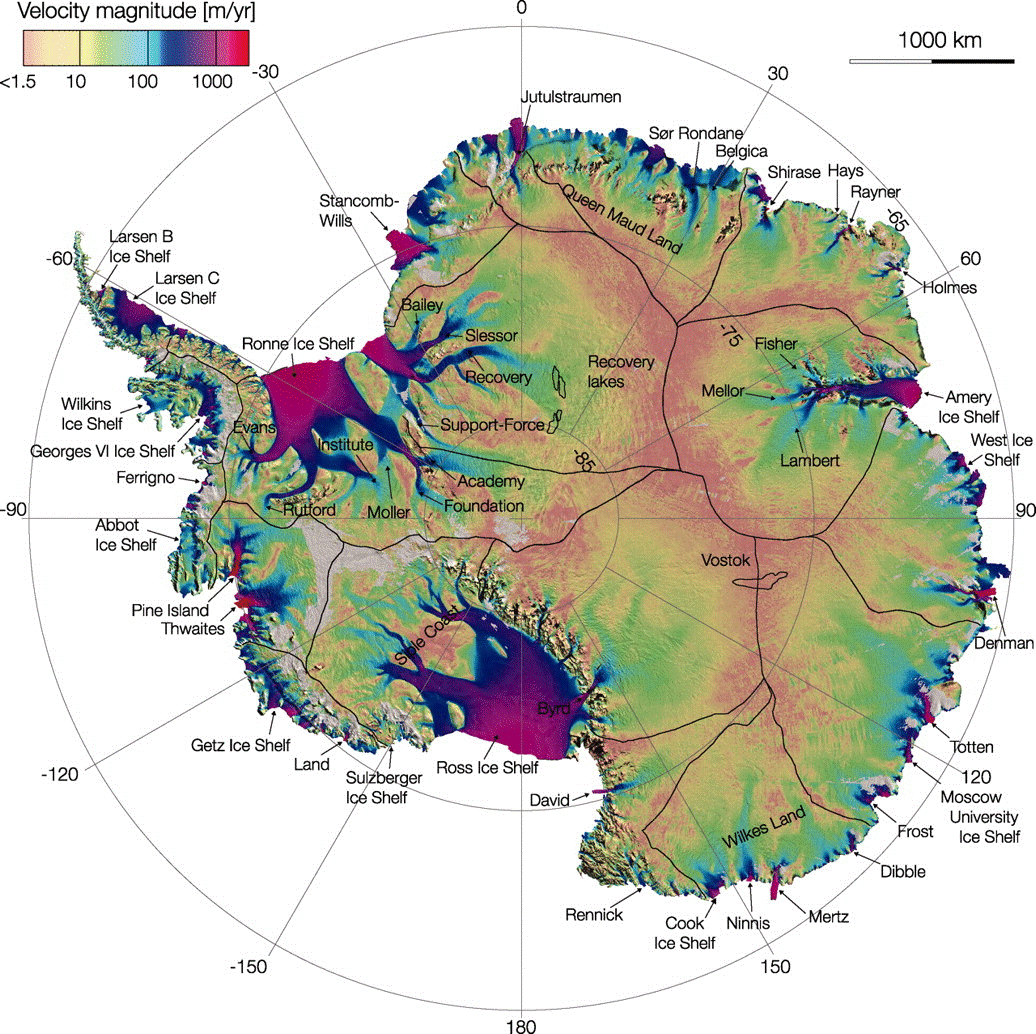
図1 ALOS/PALSAR, Envisat/ASAR, Radarsat-2, ERS-1/2のデータに基づいて得られた南極大陸の氷床/氷河の流動速度分布(Rignot, E., J. Mouginot, B. Scheuchi (2011a), Ice Flow of the Antarctic Ice Sheet, Science, 333(6048), 1427-1430, DOI: 10.1126/science.1208336). 海沿いの接地線も干渉SARの手法によって得られている(Rignot, E., J. Mouginot, and B. Scheuchl (2011b), Antarctic grounding line mapping from differential satellite radar interferometry, Geophys. Res. Lett., 38, L10504, doi:10.1029/2011GL047109.).
2. SARで分かってきた氷河氷床変動の実態
従来から氷床における質量収支の擾乱に対する氷体の応答の時間スケールはおよそ1000年といわれ, 10年やそれ以下の短い時間スケールでの速度変化はないというものであった. しかし, 一般に考えられていた以上に急に大きく流動速度が変化すると分かってきたことはSARがもたらした大きな知見である.
例えばRignot (2008)は西南極の複数の氷河において, 1970年代のLandsatデータから得られた流動速度を近年のERSやRadarsat, PALSARのデータで得られた流動速度と比較し, 1996年から2007年で場所によって40%から80%以上加速していることを示した. また, グリーンランド中西部にある最大の溢流氷河であるJakobshavn (ヤコブスハーベン)でも, 1997年から2003年の間に流動速度がほぼ2倍に達していることが分かった(Joughin et al., 2004). 一般に, 氷河表面で観測される流動速度は, 粘性流体としての氷体そのものの流動と氷体底面における滑りと堆積物の変形の和として理解される. 粘性流体としての氷河流動速度は氷厚が薄くなるほど遅くなるため, 観測された流動速度の増加は温暖化による融解で氷厚が薄くなる効果では説明できず, 表面での融解水が底面に到達したことや氷河末端部の融解で塞き止め効果が無くなったことで解釈されている. 流動速度に氷厚データをかければ流出量になる. 氷河の質量収支において, 涵養量(供給量)と融解量が変わらずに流出だけ増えれば, 氷河質量は欠損する. 無くなった質量の行き先は海であり, 流動速度の増加は海水面上昇と結びつけて議論されている.
ヨーロッパの山岳氷河では多くの地上測量観測が行われ, 春から夏にかけて氷河流動速度が上昇することが知られてきた(e.g., Iken & Bindschadler 1986). 季節変化のような“速い動き”は氷体温度の高い温暖氷河に限られると従来は思われていた. ところが, Zwally et al (2002)がグリーンランド氷床の平衡線付近でのGPS観測データに基づいて, 顕著な流動速度の季節変化を示して以降, SARデータに基づいてグリーンランドでも流動速度に顕著な季節変化があることを示した研究が数多く発表された(Joughin et al. 2008 など). 高緯度で気温も氷温も共に低い筈のグリーンランド氷床でも, 顕著な季節変化が観測されたことは意外性を持って受け取られ, 寒冷氷河や極域氷河と分類されていた氷河までも温暖氷河化するのではといった懸念されたようだ. しかし, 通常時に1km/年以上流れる氷河も100m/年程度しか流れない氷河も, 季節変化の振幅そのものは同程度であることが分かってきて, いわゆる寒冷圏の氷河も流動速度が季節変化を示すこと自体が珍しいこととは思われなくなった. ただし, 季節変化のメカニズムについての氷河水文学的な理解は比較的最近のトピックであり(Schoof 2010), 後述の冬期加速の観測とも併せれば氷河流動の短期的変動のメカニズムはまだ十分に理解されているとは言えない.
南極大陸とグリーンランドの氷河氷床に比べ, アラスカ, アジア高山域, 南米アンデス山脈などに分布する山岳氷河の流動をSARで調べることは, より困難だった. 大きな理由は, 幅も長さも短いため従来のSAR画像の空間分解能では不足すること, 高標高域の涵養量や低標高域の消耗量が大きいために衛星回帰周期間での相関劣化(干渉性の低下, コヒーレンスの低下)を起こしやすいしやすいことである. しかしこの状況は, 日本のLバンドSAR衛星ALOS/PALSARによってかなり改善された. ALOSの回帰周期は46日と長めでありながら, 雪氷層におけるマイクロ波の透過性の強さのため, 時間的な相関劣化がCバンドやXバンドのSARデータよりも少ない. その結果, ALOS/PALSARのデータにピクセルオフセット法を適用することで良質な速度場データが得られた. Rignot et al (2011)は, 各種の衛星SARデータを用いて南極大陸のほぼ全域にわたる流動速度分布を求めたが, 低標高域ではPALSARによる貢献が非常に大きい. 日本からも幾つかの新たな成果が発信された. 例えば, Yasuda and Furuya (2013)は西クンルン山脈の山岳氷河の流動速度を初めてマッピングし(図2), さらに数10年程度のサイクルで流動速度が急激に増加するサージ型氷河も存在することを見いだした. またMuto and Furuya (2013)は南米パタゴニア氷原の山岳氷河の流動速度分布の時空間変化と末端位置の経年変化をEnvisatのデータも併せて調べた. また, アラスカやカナダのユーコン地域には数多くのサージ型氷河が分布していて, サージが冬に開始する傾向にあることが経験的に知られていたが, 発生メカニズムについては不明な点が多い. Abe and Furuya (2014)はALOS/PALSARデータを用いて流動速度分布を詳細に調べ, サージしていない静穏期でも, 冬期にしかも上流で加速が見られることを見いだした. 前述のように, 氷河表面の融解水が底面に達することで夏季に加速することは常識となっている. Abe and Furuya (2014)の冬期加速は, 氷河内部や底面での水理水文学環境を支配する新しいプロセスの存在を示唆している.
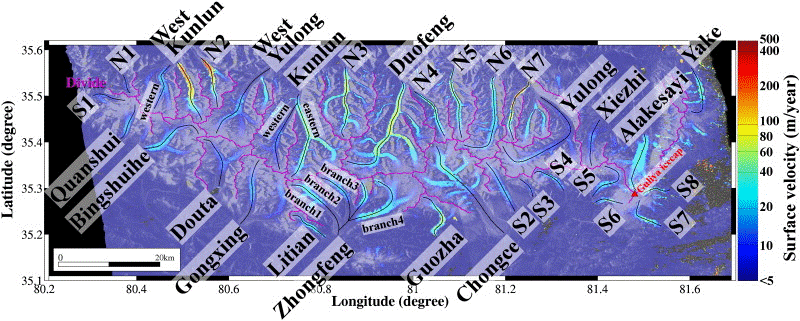
図2 ALOS/PALSARから得られた西クンルン山脈の氷河表面速度分布の一例. 表面速度の分布を対数スケールで示してある. West Kunlun氷河とN2氷河はサージが進行中である. 紫色の線は分水嶺を示し, 北側に流れる氷河と南側に流れる氷河に分けられる. 黒実線は氷河の流線を示す. (Yasuda, T., and M. Furuya (2013), Short-term glacier velocity changes at West Kunlun Shan, Northwest Tibet, detected by Synthetic Aperture Radar data, Remote. Sens. Environ., 128, 87-106, doi:10.1016/j.rse.2012.09.021)
3. SARによる雪氷圏モニターの今後
ドイツのDLRが2008年にXバンドで回帰周期11日のTerraSAR-Xを打ち上げて以来, 世界のSAR衛星は従来以上に高い時空間分解能を目指している. Xバンドでも回帰周期が短ければ, 相関劣化は少ないので山岳氷河の流動速度分布の検出も期待できる. また, 単独のSAR衛星で流動速度や接地線を求める以外に, TerraSAR-XとTanDEM-Xで行っているように複数衛星のTandem飛行によって得られたSARデータにInSARの手法を用いてDEMの逐次的な生成を行い, それに基づいた氷厚変化の測定も行われつつある. DEM differencingとも呼ばれるこの手法により, 氷河の涵養域と消耗域の高さ変化の測定が期待できるため, 流動速度データとの組み合わせによって, 氷河の質量収支に関する研究に大きく貢献するであろう.
2014年には欧州がCバンドのSentinel-1, 日本がLバンドのALOS-2を打ち上げた. 従来以上に膨大な量のSARデータが得られることで, 各種SARデータを統合活用により, 流動速度分布などはさらに詳細が分かるようになるだろう. 流動速度データに基づいて, 底面応力状態を逆問題として推定する研究や(Joughin et al 2004), 氷河流動の物理モデルに基づいた順問題の検証も従来以上に活発になると思われる.