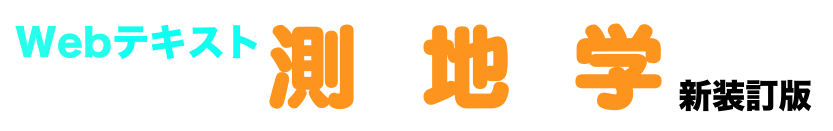地上重力測定における陸水擾乱問題
京都大学理学研究科 風間卓仁
1. 概説
重力加速度(重力)は「地球質量に伴う万有引力」と「地球回転に伴う遠心力」のベクトル和である. このうち, 万有引力は大気・海洋・岩石といった質量の分布変化に従って時間的に変化するので, その結果として重力も時間変化する. 例えば, 重力は潮汐に伴って100 μGalオーダーの振幅で時間変化するほか, 極運動や大気圧変化によっても数 μGal程度変化する(※ $1 [μGal] = 1 × 10^{-8} [m/s^2]$).
一方, 重力計(例えば絶対重力計や超伝導重力計)で測定される重力の時間変化(重力変化)はあらゆる物理プロセスから生じる重力変化の総和なので, 上述した既知の寄与を重力測定値から差し引くことで, 未知の重力変化を検出することができる. 近年では, 地震時地殻変動・火山内部のマグマ移動・雪氷の質量変化といった, 固体地球域の変動に伴う重力変化を検出できるようになってきた(→第2節に詳述). 特に, マグマ質量の移動は火山噴火に先行した現象なので, 火山における重力観測が火山噴火予測に役立つものと期待されている.
しかしながら, 重力は降水・土壌水浸透・地下水流動といった陸水分布の時空間変化にも敏感であり, この陸水起源の重力変化が擾乱(陸水擾乱)となって, 上記に示した固体地球起源の重力シグナルを覆い隠すことがある. また, 陸水擾乱は重力観測点周辺における陸水質量の時空間分布を強く反映しているので, 陸水擾乱の時間的形状および振幅は観測点の位置や観測点周辺の地形によって大きく異なる(→第3節に詳述). そのため, 陸水擾乱の物理メカニズムに関する統一的な理解は, これまで十分になされてこなかった.
ところが2000年代以降になると, 固体地球起源の重力変化の検出を目的として, さまざまな方法によって陸水擾乱をモデル化および補正する研究が数多くなされるようになってきた. 陸水擾乱モデルには, 大別して以下の通り3つ存在する(→第4節に詳述).
(a) 経験的手法: 降雨1 mmに対する重力応答を簡易な関数によって経験的に表現し, 応答関数と降雨データの畳み込み積分によって陸水擾乱を計算する.
(b) 観測的手法: 土壌水分量や地下水位といった陸水データを観測し, 陸水量変化と重力変化の間の相関関係によって陸水擾乱を再現する.
(c) 物理的手法: 土壌水浸透や地下水流動に関する非線形拡散方程式を数値的に解き, 得られた陸水分布を空間的に積分することで陸水擾乱を見積もる.
このうち, (a)(b)は陸水擾乱を比較的容易に計算できるものの, 陸水と重力の間に線形性を仮定していることが多く, その場合には実際の陸水擾乱に見られるような非線形性を表現できない. 一方, (c)は陸水流動の物理をより忠実に再現しているが, 土壌物理パラメーターや気象データといった数多くの基礎データが不可欠であり, 数値計算は容易でない.
このように, 現在さまざまな陸水モデルが提案されているものの, どのモデルにも一長一短が存在する. 今後固体地球起源の重力シグナルを精確に検出するためには, 「重力シグナルの振幅」「重力計の観測精度」「陸水モデルの擾乱再現精度」を比較した上で, 最も適切な陸水モデルを適用する必要がある.

図1 陸水擾乱の概念図
2. 固体地球起源の重力変化
Imanishi et al. (2004)は岩手・長野・京都にそれぞれ設置された超伝導重力計を用い, 2003年十勝沖地震(Mw 8.0)に伴う重力変化を観測した. そもそも, 大地震発生時には地殻変動によって上下方向に変位が生じ, 地殻内部に密度分布変化が生じる. 十勝沖地震の際には, これらの効果によって最大0.6 μGalの重力変化が観測され, 1990年代に提唱された地震時重力変化の理論(Okubo, 1992)を証明することとなった.
また, Okubo et al. (2013)は宮崎・鹿児島県境の霧島火山で絶対重力計による重力連続観測を実施し, 2011-2012年新燃岳噴火に伴う振幅約10 μGalの重力変化を検出した. 重力変化は各噴火イベントで確認され, しかも噴火のタイミングから数時間程度先行していた. またこの重力変化は, 火山深部の球状圧力源(茂木モデル; Mogi, 1958)の膨張/収縮によって説明できることから, 噴火に至るまでのマグマ蓄積/放出過程を反映していると考えられる.
さらに, Sun et al. (2010)はアラスカ南東部の6地点において2006-2008年の夏季に絶対重力計による重力測定を毎年実施し, 地面隆起に伴う-5 μGal/year前後の重力減少を観測した. そもそも, アラスカ南東部では過去および現代の氷床融解に伴うアイソスタシーによって最大+3 cm/yearを超える地面隆起が観測されている. 今後より長期の重力変化および上下変位を観測することによって, マントルの粘性率や現在の氷床融解量をより精確に把握できるものと期待される(Sato et al., 2012).
このように, 重力観測は地震・火山活動・氷床変動といった固体地球起源の変動を検出・監視することができる. しかしながら, このような重力シグナルが検出できるのは陸水擾乱の小さい時期に限られており, 例えば台風襲来期の火山噴火時には火山活動起源の重力シグナルが陸水擾乱に覆い隠されてしまう(Kazama and Okubo, 2009). したがって, 乾期・雨期に限らず固体地球起源の重力変化を把握するためには, 陸水起源の重力擾乱を適切にモデル化・補正する必要がある.

図2 十勝沖地震に伴う重力変化(Imanishi et al., 2004より抜粋)
3. 陸水擾乱の特徴
陸水擾乱は多くの場合, 「雨期に極大, 乾期に極小」という年周変化を示す. 例えば, ベルギー・Membachに設置された超伝導重力計の重力連続観測では, 多雨期の冬に極大となるような正弦関数的な陸水擾乱が観測され, 夏季/冬季間の重力差はおよそ6 μGalに達した(Van Camp et al., 2006). また, 年周変動の振幅や時間的形状は重力観測地点によって異なり, 雨期/乾期の重力差が100 μGal近くに達する地点さえ存在する(鹿児島県・桜島; 風間ほか, 2014).
一方, より短期的な重力変化に注目すると, 陸水擾乱は降水時に急激に増大, 降雨後に緩やかに減少する. 例えば, 群馬・長野県境の浅間山に設置した相対重力計では, 豪雨時に+20 μGalの急激な重力上昇, および豪雨後に-0.5 μGal/dayの緩やかな減少が観測された(名和ほか, 2009). また, 降水1 mmに対する重力応答量や降水後の重力変化速度はやはり観測地点によって異なり, 地下に設置された重力計では降水に対する応答の正負が逆転することが知られている(Abe et al., 2006).
以上のことから, 陸水擾乱は重力観測点周辺における陸水量の時間変化を反映しており, 陸水分布の空間不均質が陸水擾乱の観測点依存性を生んでいるものと考えられる. そもそも, 陸水擾乱は重力だけでなく傾斜・伸縮など多くの測地データで古くから確認されており(竹本, 1967), 測地学において約50年もの長きに渡る未解決問題である. 測地データから固体地球起源の変動を詳細に理解するには, 陸水学の物理に基づいて陸水擾乱をモデル化・補正することが不可欠なのである.
なお, 年1回程度の定期的な重力測定の場合には, 重力測定を毎年少雨の同一時期に実施することにより, 陸水擾乱の年周成分の寄与を最大限低減することができる. 例えば桜島火山では, 「降雨が比較的少ない」「冬季に比べて温暖である」などの理由から, 毎年10-11月にハイブリッド重力測定が実施されている(山本ほか, 2013). しかしながら, 陸水擾乱は各年の降水量の違いによって経年的な変化も示すため(Bower and Courtier, 1998), 上記の観測スケジュールを取っても陸水擾乱を完全に排除することはできない. このような観点からも, 陸水学に即した陸水擾乱のモデル化が必要であると指摘できる.

図3 ベルギー・Membachで観測された年周的な陸水擾乱(Van Camp et al., 2006より抜粋)
4. 陸水擾乱のモデル化
陸水擾乱のモデル化で広く利用されているのが経験的手法である. この方法では, 単位降水当たりの重力応答(降水時の急激な上昇, および降水後の緩やかな減少)を簡易な関数によって経験的に表現し, 応答関数と降雨データの畳み込み積分によって陸水擾乱を計算する. 例えばHarnisch and Harnisch (2006)は, 降水応答を2つの指数関数の積によって表現し, 世界各地の超伝導重力計で観測された陸水擾乱を再現した. またImanishi et al. (2006)は, 降水応答が鋸歯形(きっしけい; ノコギリの歯のような形)になると仮定し, 長野県・松代で観測された陸水擾乱を±1 μGalの精度で再現した. このように, 経験的手法は比較的容易に陸水擾乱を再現できるものの, 陸水の非線形的流動から生じる陸水擾乱の非線形性を考慮できない. また, 本モデルで作成された応答関数はあくまで経験的なものなので, 本手法の陸水擾乱補正によって固体地球起源の重力変化をも差し引いてしまう可能性がある.
一方, 陸水擾乱のモデル化のため古くから用いられてきた方法として観測的手法がある. この方法では, 重力データと同時に土壌水分量・地下水位といった陸水データを並行観測し, 陸水量変化―重力変化間の相関関係によって陸水擾乱を見積もる. 例えば花田ほか (1990)は, 岩手県・胆沢扇状地の絶対重力計で観測された重力変化が, 周辺の地下水位変動と+16 μGal/mの比例関係にあることを示した. またVan Camp et al. (2006)は, 重力観測点の周辺で観測された土壌水分分布を数値的に空間積分することによって, 超伝導重力計の重力変化を±1 μGalの精度で再現した. このように, 本手法では陸水データと既知の相関関係によって陸水擾乱を容易に計算できるという利点があり, 最近では全球陸水モデルを用いた陸水擾乱解析の研究もある(Boy and Hinderer, 2006). しかしながら, 取得した陸水データが重力観測点周辺の陸水量を代表しているとは限らないので, 重力変化と陸水量変化の間に明確な相関関係が確認できない場合も存在する.
上記2つのモデルの欠点を補えると期待されているのが, 物理学的手法を用いた陸水擾乱モデルである. この方法では, 土壌水浸透や地下水流動に関する非線形拡散方程式(Jury and Horton, 2004)を数値的に解き, 得られた陸水分布を空間的に積分することで陸水擾乱を見積もる. 例えばAbe et al. (2006)は, 超伝導重力計の周囲6 mの土壌水分布を土壌水浸透の物理方程式によって計算したところ, インドネシア・バンドンで降雨時に観測された重力変化(振幅約0.5 μGal)のうち約8割(約0.4 μGal)を再現した. また, Kazama et al. (2012)は約2年間に渡る土壌水の時空間分布を数値的に見積もり, 岩手県・胆沢扇状地の重力連続変化を±1 μGalの精度で再現した.
さらに, この物理モデルを浅間山(群馬・長野県境)に適用することにより, 台風襲来に伴う陸水擾乱に埋もれていたマグマ移動起源の重力変化(振幅約5 μGal)を抽出することに成功している(Kazama et al., 2015). このように, 物理的手法は汎用性が高く, あらゆる地域の陸水分布および重力擾乱を物理学的背景に即して再現できる. 多くの基礎データ(気象データ・土壌物理パラメーター等)が要するという欠点があるものの, 重力連続観測に対してこの物理モデルをリアルタイムに適用すれば, マグマ移動をはじめとした固体地球内部の変動を忠実に監視できるものと期待される.

図4 物理モデルによって計算された浅間山の陸水擾乱(Kazama et al., 2015より抜粋)